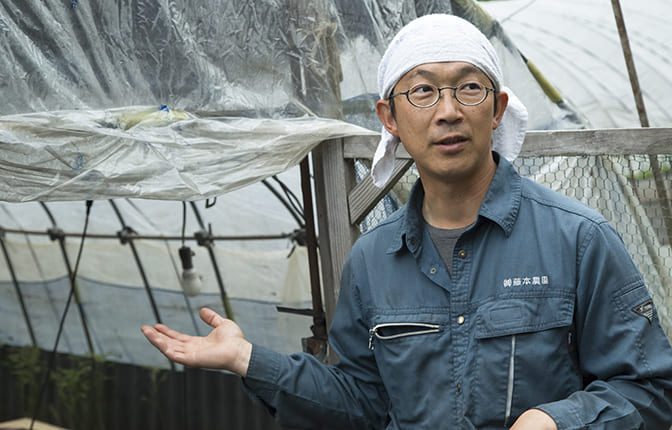聡さんが父の勲さんから代替わりしたのが30歳の時。そのタイミングで藤本農園は法人化して聡さんが代表に就任したが、聡さんは「ずっと悩み続けていた30代だった」と振り返る。
20代の時から勲さんと共に米づくりに勤しんできたが、勲さんの作業スピードや技術などを全て自分の身に付けることができていたかというと、30歳を過ぎてもそうは思えなかった。父から学んだことをきちんと実践でき、その上で自分の形に落とし込めるようになったのは、もっと後だという。
この段階に到達して初めて、これまで父の勲さんがひたすら進み続けてきた「農家」としての道から、より経営や商業にシフトした「農産業」という方向に、聡さん自身のスタンスを見出すことができた。この中山間地域でこの先もずっと米をつくり農家が生き続けていくためにはどうしたらいいか。イノシシなどの害獣、自然災害の増加、水資源の確保などさまざまな課題や問題を抱え、何より米の消費量が減少している中で、やみくもに作付面積を拡大して収穫量を増やすのは得策とは言い難い。
スケールメリットで勝負するのではなく、米の真価を問い、究極の米とは何かを追究して、安全性やおいしさなどの品質と向き合い、なおかつそれがお客さんにきちんと伝わる仕組みを構築しなければ、米は単なる「白い物体」で終わってしまうと、聡さんは考えている。
米は毎日のように食べられるものだが、収穫できるのは年に一度。お客さんにとってとても身近でありながら、伝えきれていない物語が、米にはある。ただの白い物体で終わらせないために、作り手の姿や米が育つ景色を、毎年、毎日のように伝え続けることが、米が抱える課題に直面し栽培条件に恵まれているとはいえない中山間地域の農家が戦う武器となり得るのではないか。このような分析を起点に、聡さんはこの町の米の未来をつくるための「戦い」に向けて準備を始めた。
「お客さんは安心・信頼できる米を求めているものの、購買行動に行き着くまでに途切れてしまいがち。テレビで見て欲しくなる→商店に行く→欲しい品物がない→探す。ここまでは行動しても、その先、さらに品物がなかった時に、なんとしてでも出会うまで探し出すにはなかなか至らない。だからわれわれ農家も待っているだけではなく、こちらから一歩前に出て、探し物はここにありますよと、信頼できる情報を発信していかなければならないのです。お客さんと販売店が交わるだけでなく、もう一つ、農家が関わって、価値ある情報を、お客さまが取り込みやすい形や手段で発信することが大切です。それが情報誌なのか、ラジオやテレビなのか、体験の場なのか。穂が出たよ、アイガモが帰ったよ、田んぼが黄金色に染まるよ、台風で稲が倒れたよ…そんなふうに良い情報も悪い情報も全て発信することで、飽きられることのない物語を伝えていけるのではないかと考えています」。
作るだけでなく、伝えて、売り、継承することの重要性をより意識し、生産だけではなく、農業の情報を発信できる生産者でありたい。その志を体現する取り組みの一つが、現在敷地内に建設中の事務所と直売所を兼ねた情報発信施設だ。
最初は、ふらっと立ち寄った人がお米を買いたいと希望した時に、つきたてを提供したいという発想から。それなら試食もできたらいいねと試食スペースを追加。さらに、余ったお米は検食がてらに従業員で食べれば、従業員食堂ができるねというところから、キッチンを追加。せっかくキッチンをつくるなら将来的にカフェを営業できるスペースを確保しておいた方が…そんなこんなで夢が広がり、夢の分だけ施設のスペースも広がっていった。「新たな挑戦ですが、現在の農業が秘めた本当の価値、自分たちが感じている価値をきちんと伝えられる時期が来たのかなとワクワクしています」。
キッチンができたらぜひ実現したいと聡さんが計画しているのが、おいしいお米の炊き方を自ら撮影してYouTubeで発信すること。お客さんからどうしたらお米をおいしく食べられるかと聞かれることが多く、その際にインターネットで検索すれば動画がいくらでもありますよと答えるのではなく、「自分たちで制作した動画をぜひ見てください」と答えられたら、自分たちの商品を見てもらうチャンスが生まれると聡さんは考えている。そしてお客さんが自分たちの商品を知った時、おいしさや感動が一緒に付いてくれば、それが他社商品との差別化となり、選ばれる理由となるはず。
炊き方や保存方法など役立つ情報はもちろん、せっかくなら楽しんでもらえる仕掛けを施したいなど、動画の内容については思案中。子どもたちには「お父さんはYouTuberになるよ」と宣言しているそうだ。
新しい施設は直売機能を備えてはいるが、ここでの販売を伸ばすことが目的ではない。あくまでも藤本農園の米の情報発信基地として、米について知ってもらい、興味を持ってもらい、毎日の中に取り入れてもらうためのきっかけになることが、この施設の存在意義となる。
こちらからお客さんに提供するだけではない。たとえば、これだから米を食べにくい、こうなればもっと米を食べたいなどお客さんの声を聞いたり、米の販売店がどうやって売れば良いのか迷った時に答えやヒントを提供したり、米に興味を持ってここで働きたい、就農したいという人が出てきたり。米を介して人の思いが通い合う場としての期待が高まる。
このような新しい挑戦も、生産技術と環境が伴わなければ説得力をもたない。「農業に就いて20年間、20回、米を作ってきましたが、毎年課題が出てきます」と言うように、試練の連続だ。「だけど待ってくれているお客さんがいて、米のコンクールで受賞した時はみんなで喜んでくれて、その後ちょっと落ち込んだ時期もありましたが、再び賞を穫った時にはまた同じように『待ってました!』と喜んでくれました。あの姿を見た時に、自分が研究し続けること、毎年種をまいて、しっかり育てよとあれこれ手をかけることには意味があるんだと思ったんです」。
真摯に向き合っているからこそ、毎年「しんどい」面もある。聡さんは40歳を越え、当然、これから年を重ね体力も衰えていく中で、10年先も今と同じように田んぼに立って、変わらぬ情熱と精神力を保ちながら動き続けることは容易ではないだろう。
だからこそ、若い人にも技術を伝えて男女問わず農業に参入しやすい環境、この地域で米を作りやすい環境を整えることを、課題の一つとして取り組んでいる。たとえばハイテク機械を導入したトラクターの自動化に関する実証実験に参加するなど、新技術を積極的に取り入れていくつもりだ。
これまで農業といえば男性中心のイメージだったが、女性、高齢者、障がい者でも楽に農作業ができるような環境をつくらなければ、本当に後継者がいなくなってしまうと、聡さんは強い危機感を感じている。「先日、息子に初めて草刈り機を使わせたのですが、電動の草刈り機は軽く、音が静かなので指導しながら作業できるんです。中学生になったばかりの息子は体も小さいのですが、扱いやすい技術を提供して最初からきちんと指導できれば機械を使えるようになる。これからの農業はこうでなければならないと思っています。ハイテク機械を導入するにはコストがかかりますが、それが可能な農家が積極的に投資して、安全で確実な作業を補佐できれば、農業に参入するハードルが下がり、後継者を育てることができます。そして自分たちは後継者を育てながら、自分自身の情熱もずっと変わらず結果に結びつけられるような仕組みを、50歳までにつくっていかなければと思っています」。
東城町は高齢化が進んでおり、農家を辞める人から藤本農園へ農地を託されるケースがさらに増えることが予想される。「それはすごくうれしいことですし、応えなければこの地域の農業が廃れてしまう危険性もあります。だからそれを吸収できる体力をつけていきたい。そうすると面積が拡大するわけですから、売り先をきちんと確保し、お客さんが買いたくなるようなムーブメントを起こしながら自分自身の基礎を固め、販売と生産の地盤を固めるのが課題です」。
30代で悩みながら積み上げてきたものを40代で反映し、日本全体の米の市場が縮小しても、この地域の米だからこそ食べたいというお客さんを育てていくこと、そのために米のエンターテインメント性を高めていくことが藤本農園の使命だという。
「私たち農家が昔から見てきたお米を食べる姿は、とうの昔に変わっています。今この時代に、自分たちが提供している量が適正かどうか、その姿形が手に取りやすいのかどうか、お客さんの実情と大きく剥離してしまっている部分をどうにかして近づけたいと考えています。面白いから手に取ってみたいなと思わせるところまでが、私たち農家に準備できるお米の付加価値。長年続けてきた農薬を使わないアイガモ農法米を提供し、その価格が高いと思う人には、農薬を減らしたもう少し求めやすい価格の米をというように、幅広い商品を取り揃えることによって、お米を特別な時にも普段にも使えるような存在にしたいんです」。
身近な存在であり、藤本農園のお米に携わる全ての人の健康と、おいしい! の笑顔が確実に確保できること、その米を作る自分たち藤本農園の従業員も健康で笑顔であること。その願いと誓いが藤本農園の社訓「一粒万笑(いちりゅうまんしょう)」に込められている。「一粒で万の笑顔を作る姿を若い人や自分の子どもたちに見てもらって、人を喜ばせることのできる仕事、人を喜ばせることのできる大人を目指してもらいたいですね」。
農薬を使わないアイガモ農法があったおかげで、農業を嫌いにならずにすんだと聡さんは言う。「じゃあ農薬が悪なのかというと、決してそうではなくて、農薬の存在が農家の収益拡大と経営の確立に大きく寄与したわけですから、そこにつばを吐きかけることはとてもじゃないけどできません。現在の農薬は安全性にも配慮されているので適切に使用すれば安全性を心配する必要はありません。農薬を使用していない米もそうでない米も、どちらか一つに特化しなければならないと決めつけるのではなく、幅広いお客さまに喜んでもらえるものが用意できれば、企業経営としてはそれも一つの価値になります。そのような姿勢で栽培に携われば、企業として、お客さまの喜ぶ顔と健康を提供することを約束しますと宣言できるのではないかと思います」。
父の勲さんは農業をするに当たって「環境に優しく」「地域に優しく」何より「消費者に優しく(消費者を裏切らない)」という三本柱を大事に守り、そのおかげで今に至るまで藤本農園は信頼を得ることができている。聡さんに代替わりしても、大事なものは変わらない。
聡さんは広島県内の小学校や高校、大学などで子どもたちを対象とした食育も担っている。「理解できた時や面白いと感じた時は、子どもたちの目が輝きます。難しいことを言うと目から光が消える。伝える力は子どもたちに鍛えられましたね」。
子どもたちに必ず伝えているのは、農家は、水を守り、土を守り、種を守っており、このどれか一つでも汚染されるなどして取り返しの付かないことになってしまうと、未来を犯してしまうことになるのだということ。だから聡さんは「新しい品種ができるとか、新しい可能性が広がるのはいいことだと思います。ただそのために在来のものを駆逐し、在来が持つ可能性まで潰してしまうのは違う。ましてやそれがただの儲け主義の中で起きてしまうとすれば、未来が取り返しの付かないことになることだってあります。農家は種の多様性を肝に銘じ、自分たちは未来のために汚してはならないものを扱っているのだという自覚のもと、消費者に提供するものに責任をもたなければなりません。米は1年に一度しか収穫できないものだからこそ、来年のために種も環境も残しながら、お米の未来を背負っているのだという責任を感じなければ」と、安易な競争に警鐘を鳴らす。
さらに「食べる人たちにも、米づくりの現場を体験してもらうことで、普段当たり前に買っている米は、自分たちが食べることで来年も、その次も、食べ続けることができるのだということを実感してほしい。誰にも食べてもらえず余った米を大量に捨てることを繰り返していれば、必ずや将来自分たちの首を絞めることになるんです。その代わり私たち農家は、食べてくれるお客さんがいる限り、台風だろうが大雨だろうが、お届けできるように精一杯頑張ってつくる姿を示す。そうすることで、安心と信頼が生まれるのだと思います」。
「現代の日本では飢えに苦しむ子どもたちは少ないので、食べ物がなくなったらどうするのかと言われてもピンときません。だけど、おいしいものを食べると喜び、たとえばアイガモの肉を食べてうれしそうな子どもたちに対して、食べたら笑顔になったでしょう、おいしくて幸せだったでしょうと尋ねるとうなずきます。そこで、この笑顔を届けたくて私たち農家は食べ物を作っているんだということを伝え、だから将来は笑顔を作る仕事、人を笑顔にできる大人になってほしいと話しています。この仕事は命をかける仕事ではなく、一生をかける仕事だから、私たち農家が一生かけて頑張っていることが伝わればうれしいですね」。
聡さんには二人の息子と一人の娘がいる。これまでピザ屋やパスタ屋、パン屋になりたいと言っていた長男が、最近ようやく小麦から脱却して「お父さんの後を継いでもいいよ」と言い始めたという。実際のところはまだ未知ではあるが、直売所をつくる計画を打ち明けると目を輝かせたそうだ。
「うちの子どもたちは、うちの米を食べてくれる人が笑顔になる光景を間近で見ているから、自然とその喜びを共感してくれているのでしょう。だから自分の子どもたちにもぜひそんな仕事に携わってほしい。だけど私と全く同じである必要ななく、カフェ経営でもピザ屋でも何でもいい。ただし、ぼんやりとした夢ではなく、大きな土台の上に見る夢であってほしいと思います。グラグラ揺れながら何かを求めてあちこちふわふわ探し回るのではなく、コレだという土台に足を着けた上で広い視野で行動するような」。
自分の夢を追いながらも、人や地域や自然環境に迷惑をかけてはならない。そんな厳しさも教えながら、わが子を見守っている。「娘は農家アイドルになってもらいましょうか(笑)」なんて冗談を飛ばしつつ、堪忍袋の緒を太く保ちながら、まだまだ先の長い成長を楽しみにしているようだ。 ちなみに次男の夢は「きかんしゃトーマスの運転手」。いつかトーマスから田植機やコンバインに乗り換えてくれる日が来るのか。そちらもお楽しみの一つだ。
掲載記事内容は取材当時のものであり、
現在の内容を保証するものではありません。